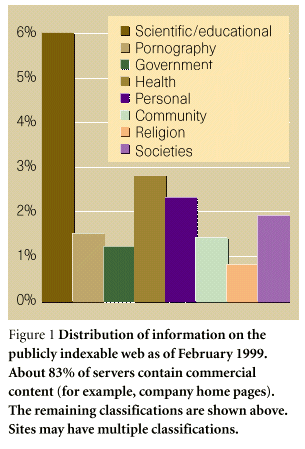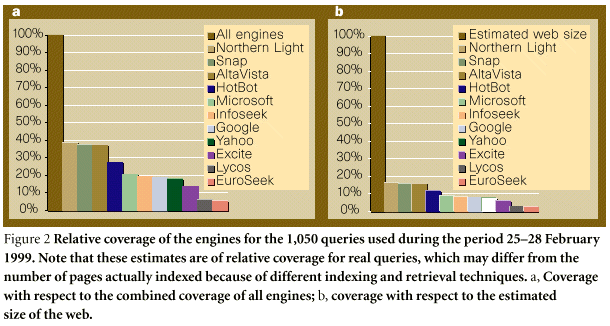戻る
平成11年度北日本地区図書館研修
1999年9月29日 宮城県図書館
インターネットを使ったレファレンス
目次
1.インターネット
【参考文献1】
2.Webと商用DB
3.ハイブリッド図書館に向けて
【参考文献2】
4.図書館とインターネット
4-1.自己研修と情報収集
4-1-1.情報を探して使う
4-1-2.自宅のネットワーク環境の整備
【参考文献3】
4-2.設置母体や図書館の基盤整備
4-2-1.アクセス
4-2-2.管 理
4-2-3.サービス内容
4-3.図書館員にとって有用なサイト
4-3-1.インターネットにおける情報検索の有効活用
4-3-2.検索エンジン
4-3-3.文献検索
4-3-4.各種DB
4-3-5.図書館関連・リンク集
4-3-6.インターネット関連
4-3-7.電子雑誌
【参考文献4】
4-4.インターネットの課題
4-4-1.図書館にとってのインターネット
4-4-2.インターネットにとっての図書館
4-4-3.図書館とインターネット
4-4-4.問題点
【参考文献5】
5.インターネットを使った情報検索演習
◆例題1◆第2回検索の鉄人 第一次予選・ラウンド2
1998年6月19日~6月25日
◆例題2◆第2回検索の鉄人 第一次予選・ラウンド4 1998年7月3日から7月9日
◆例題3◆各県のインターネットの状況を調べる 1998.1のURL
◆例題4◆図書や雑誌の所蔵
◆例題5◆事項調査
◆例題6◆特定サイトからの検索
◆例題7◆全文データの検索
◆例題8◆海外の検索
◆例題9◆検索困難な事例
(資料1)図書館における電子化、情報化の背景
1-1 高度情報通信社会推進に向けた基本方針
平成10年11月9日 高度情報通信社会推進本部決定
1-2 大学図書館における電子図書館的機能の充実・強化について(建議)平成8年7月29日
学術審議会
1-3 図書館の情報化の必要性とその推進方策について--地域の情報化推進拠点として(報告)
1-4 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について(答申)(平成10年7月29日
教育課程審議会)
(資料2)情報リテラシー:パソコンとインターネット
1.パソコンの操作
1-1.オペレーションシステム:Windows
1-1-1.キー操作
1-1-2.日本語入力:ATOK
1-1-3.エクスプローラー
1-2.アプリケーション
1-2.1.ワープロ:Word
1-2-2.表計算:Excel
1-2-3.通信ソフト:秀Term
1-2-4.画像編集:Paint Shop
1-2-5.ブラウザ:Netscape
2.インターネットの利用
2-1.インターネットとは何か
2-2.インターネットの仕組み
2-3.電子メール:インターネットはメールに始まりメールに終わる
2-4.WWW
3.ドキュメントの作成と管理
3-1.共有の思想
3-2.作成の技術
3-3.ドキュメントの管理
1.インターネット ↑
-
インターネット:相互接続されたネットワーク。個々のネットワークはドメイン名(tsurumi-u.ac.jp[機関名.組織の種類.国名]など)で表される。ac
= 教育および学術機関:学校や専門学校、大学の研究室、co = 企業(または営利法人):株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、など一般の「会社」、go
= 政府機関、各省庁所轄研究所、or = 団体:財団法人、社団法人、宗教法人、監査法人、その他「営利」を目的としない団体、ne
= ネットワークサービス(「or」ドメインの一部がこのドメインに移行)、ad =
JPNIC会員:JPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター:インターネット・ドメイン名
などを管理する社団法人)の会員用のドメイン、gr = 法人格を有しない団体を割り当て対象とするドメイン名
(「or」ドメインの一部がこのドメインに移行)
-
WWW(World Wide Web):ハイパーテキストやリンクを使った情報提供システム。インターネットで最も利用されるシステム。Webともいう。ネットスケープ・ナビゲーター(Netscape
Navigator)やインターネット・エクスプローラー(Internet Explorer)などのブラウザーで利用する。
-
ハイパーテキスト:文書、画像、音声、動画などの様々な種類の情報を相互に関連づけて参照したり引用したりする概念。これを実現したのがWWWである。HTMLにより記述する。
-
ブラウザー:HTMLによって記述された情報を表示するためのソフトウェア。ブラウザーはインターネット上で無償で配布されたり、雑誌の付録のCD-ROMに収録されている。最近のパソコンには最初から附属している。
-
HTML(Hyper Text Markup Language):ホームページのレイアウトを記述するための言語。文書の中に書式属性を定義する「タグ」を埋め込んだテキストファイルを、ブラウザーは「タグ」の指示する属性を解釈して表示する。
-
ホームページ:WWWで提供される情報画面のことで、HTMLを使ってWWWブラウザーに表示できるように記述したファイルの集合体のこと。特に、いくつかのページで構成されるホームページの目次や先頭のページをトップページと呼ぶ。
-
サーチエンジン:いわゆる情報検索システム。インターネット上に存在するあらゆる情報を検索して、その情報の存在するホームページへのリンクを表示する。
【参考文献1】
-
平成11年度 大阪市立大学インターネット講座「
 WWW(World
Wide Web)」 <http://www.media.osaka-cu.ac.jp/~harumi/vuniv99/> WWW(World
Wide Web)」 <http://www.media.osaka-cu.ac.jp/~harumi/vuniv99/>
-
平成10年度 大阪市立大学インターネット講座「
 インターネット概論」 <http://www.media.osaka-cu.ac.jp/~nakano/vuniv98/> インターネット概論」 <http://www.media.osaka-cu.ac.jp/~nakano/vuniv98/>
-
Cronin, Mary J.(ボストン大学図書館);黒川利明監訳. インターネット : ビジネス活用の最前線.
インターナショナル・トムソン・パブリッシング・ジャパン, 1994.10, 290p. 原書名:Doing
business on the Internet ; How the electronic highway is tranforming American
company. 1993
-
インターネットのこと全部教えます Part.1. ASCII(アスキー出版) 1994年9月号,
p.245-268 (1994.9)
-
村井純. インターネット. 岩波. 1995.11, 206p. (岩波新書)
-
古瀬幸広; 廣瀬克哉. インターネットが変える世界. 1996.2, 209p. (岩波新書)
-
奥乃博. インターネット活用術. 岩波書店, 1996.11, 112p.
-
古瀬幸広. インターネット活用法:可能性を広げるコツとヒント. 講談社ブルーバックス,
1996.7, 205p.
-
村井純. インターネットII--次世代への扉. 岩波. 1998.7, 202p. (岩波新書)
|
2.Webと商用DB ↑
Webより商業DBの付加価値サービスは格段に優れている。量的には2.5倍、質的にはWebに多い娯楽は皆無である。レファレンスでは、本来はこちらが主体である。
| |
Alta Vista |
DIALOG+DataStar |
比較 |
| ページ数 |
4000万ページ |
10億件 |
|
| ワード数 |
200億語 |
5000億語 |
Alta Vistaの25倍 |
| バイト数 |
100ギガバイト |
2.5テラバイト
さらに
画像4テラバイト
索引2.5テラバイト |
毎年1億件増加
5年間で倍増の予定
(1.5倍?) |
【1997.2.14 (財)データベース振興センター主催 国際データベースセミナーによる】
大学図書館や海外の公共図書館では、データベース提供会社と年間の固定料金契約を結び、来館者や自宅から図書館にアクセスする非来館者へ、無料で商用DBを提供している。
CD-ROMでのパッケージ商品を購入し、CD-ROMサーバーによりイントラネットで構内への利用者に提供する形態が一般的である。インターネット経由でDBにアクセスできる年間固定料金サービスも出現している。
JICSTの大学向けのJOISの固定料金サービスが1999年秋から開始される。大学図書館より公共図書館の利用者数は圧倒的に多いので、当面は大学向けサービスに限定されるらしい。
|
Library
|
Public
1997(1996)
|
|
Academic
1997(1996)
|
|
Special
1997(1996)
|
|
|
Total
|
100%
|
|
100%
|
|
100%
|
|
| Unspecified |
3.12 (2.19)
|
+
|
4.05 (3.79)
|
+
|
0.32 (0.41)
|
|
| Database fees |
2.35 (2.07)
|
+
|
2.17 (2.06)
|
+
|
1.38 (1.67)
|
-
|
| Preservation |
0.67 (0.65)
|
|
2.23 (2.47)
|
|
0.31 (0.34)
|
|
| Machine readable materials |
2.67 (2.40)
|
+
|
3.42 (2.83)
|
+
|
0.5 (0.53)
|
-
|
| Microform |
2.05 (2.42)
|
-
|
2.88 (2.77)
|
+
|
0.26 (0.28)
|
-
|
| AV equipment |
0.47 (0.54)
|
|
0.81 (0.79)
|
|
0.09 (0.11)
|
|
| AV materials |
8.77 (8.43)
|
+
|
1.51 (1.56)
|
-
|
0.18 (0.19)
|
-
|
| Manuscripts & archives |
0.07 (0.04)
|
|
0.2 (0.18)
|
|
0.13 (0.19)
|
|
| Periodicals |
11.9 (12.55)
|
-
|
50.98 (50.34)
|
+
|
20.65 (20.62)
|
+
|
| Other print materials |
1.3 (1.24)
|
|
1.28 (1.44)
|
|
46.28 (45.88)
|
+
|
| Books |
66.63 (67.47)
|
-
|
30.48 (31.77)
|
-
|
29.9 (29.68)
|
-
|
米国における館種別の資料費比率(1997年度) 【[Bowker Annual Library and
Book Trade Almanac. 43rd. 1998及び42ed. 1997]より作成】 <http://www2d.biglobe.ne.jp/~st886ngw/diary/diary1008.htm#bm990126-2>
3.ハイブリッド図書館に向けて ↑
今後の図書館サービスのキーワードは、図書館のハイブリッド化である。雑種(Hybrid)には、しばしば雑種強勢とよばれる現象がおこり、親よりも長生きで成長もはやく、丈夫だという傾向がみられる。(株)トヨタは、ガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせて、地球温暖化の原因とされるCO2削減および、省エネルギーを念頭に、既存のガソリンエンジン車の2倍の燃費を実現するとともに、排出ガス中のCO、HC、NOxを規制値の約1/10に低減した車「プリウス」を開発した。同様に、図書館のハイブリッド化も可能なのではないかと考えた。この車の開発のコンセプトには、環境取組プラン「ECO-PROJECT」がある。ハイブリッドという技術のバックボーンには、社会や消費者を視野に入れたコンセプトが必要であって、優れたコンセプトがあってこそ難しい局面を乗りきることができる。ハイブリッド図書館を展開すると以下のようになる。
-
高度化:電子媒体と紙媒体をミックスした資料提供を行う。電子媒体の資料では、受入業務、書架スペース、職員さえも不要になり、サービスは向上する。しかし、経費的には拡大する。
-
効率化:組織の統合や蔵書構築方針の転換によって図書館サービスの再構築を行う。ドキュメントデリバリーや電子媒体の資料による資料提供に資料費の一部をシフトし、対外的に図書館サービスを活性化する。大学経営や自治体経営にとっての効率も考慮する。しかし、従来のやり方に安住している図書館員が効率化の障害として立ちはだかってくるだろう。
-
共生化:関連業界とのマルチソーシング(共同運営)による共生進化を推進する。従来、図書館が行っているテクニカルな業務(発注、受入、目録)などの業務を外注(アウトソーシング)することにより、関連業界は新たなビジネスを獲得でき、図書館は浮いた人員で図書館サービスを拡大できる。図書館は、単純な文献提供から一歩踏み込んで、個人的な研究テーマに沿った文献リストの作成や、学生への授業のための教材作成の援助などの、情報の評価・加工にまで機能を拡大し、設置母体との協力関係を強めるべきである。
-
グローバル化:経済と情報のグローバル化に対応した図書館のポジショニングを明確にする。既存の枠組みにとらわれないグローバルな観点から、情報・出版業界と協力して、情報流通サイクルを円滑し、情報へのアクセスを活発にし、情報の需要と供給を喚起する。図書館も流通サイクルに応分の費用を積極的に負担すべき。
大学と地域のグローバルな結びつきも活発になっている。(財)大学コンソーシアム京都では「地域社会、産業界、大学の新たな連携を構築し、大学教育、地域社会、産業界の活性化に寄与する」事業を推進しており、図書館に関連する事業として、大学間の単位互換や図書館の一般公開が行われている。
以上の手段を総動員して、ハイブリッド図書館へと自己改革し、図書館の機能拡大・強化に取り組むことが今後の図書館運営における課題となる。
【参考文献2】
4.図書館とインターネット ↑
文部省調査「公立図書館の新しい情報サービスについて」の結果概要(文部省の調査)
1998年8月1日現在/対象:公立図書館2,423館/回答館数:1,851館,回収率:76.4%
|
都道府県立 |
市(区)立 |
町村立 |
全体 |
都道府県立 |
市(区)立 |
町村立 |
全体 |
|
全館数
|
67
|
1,510
|
846
|
2,423
|
|
|
|
|
|
回答館数
|
60
|
1,179
|
612
|
1,851
|
90.0%
|
78.0%
|
72.3%
|
76.4%
|
| コンピュータ導入 |
59
|
1,066
|
474
|
1,599
|
98.3%
|
90.4%
|
77.5%
|
86.4%
|
| 業務へ外部DB |
46
|
332
|
210
|
587
|
76.7%
|
28.2%
|
34.3%
|
31.7%
|
| 業務へ有料DB |
15
|
49
|
22
|
86
|
25.0%
|
4.2%
|
3.6%
|
4.6%
|
| 業務へ無料DB |
46
|
311
|
202
|
|
76.7%
|
26.4%
|
33.0%
|
|
| 代行検索へ外部DB |
15
|
131
|
119
|
265
|
25.0%
|
11.1%
|
19.4%
|
14.3%
|
| うち予算措置あり |
4
|
27
|
27
|
58
|
|
|
|
|
| 代行検索へ有料DB |
3
|
9
|
1
|
13
|
5.0%
|
0.8%
|
0.2%
|
0.7%
|
| うち料金徴収 |
2
|
2
|
1
|
5
|
|
|
|
|
| Internet端末公開 |
4
|
23
|
37
|
64
|
6.7%
|
2.0%
|
6.0%
|
3.5%
|
| うち料金徴収 |
0
|
1
|
8
|
9
|
|
|
|
|
| うち検索費用の予算措置あり |
2
|
8
|
21
|
31
|
|
|
|
|
| HP開設 |
27
|
175
|
38
|
240
|
45.0%
|
14.8%
|
6.2%
|
13.0%
|
| HP所蔵検索 |
13
|
55
|
3
|
71
|
21.7%
|
4.7%
|
0.5%
|
3.8%
|
| 電子メール受付 |
15
|
36
|
30
|
81
|
25.0%
|
3.1%
|
4.9%
|
4.4%
|
| 職員研修実施 |
34
|
365
|
112
|
511
|
56.7%
|
31.0%
|
18.3%
|
27.6%
|
学術研究、ビジネス以外のデータベースが少ない。新聞と雑誌の記事検索ツールが未発達である。一般人の使えるようなデータベースを、社会基盤の整備として、公的資金で編集・提供するように求めることが図書館の仕事である。
1999年2月5日 神奈川県図書館協会研修会「図書館員のためのホームページ入門」
| インターネットを職場でみることができる |
5割(40名中20名) |
| 電子メールを使える |
4割(40名中15名) |
| 個人でプロバイダと契約している |
2割(40名中9名) |
| 自分のホームページをもっている |
1割(40名中3名) |
1997年3月20日 都立中央図書館「インターネット入門」
| 図書館はインターネットを使った方がよい |
全員賛成 |
| 個人で電子メールを使える |
1割(80名中9名) |
| インターネットをみたことがある |
全員 |
| 個人でホームページを持っている |
ゼロ |
| 勤務先にインターネット公開端末がある |
2.5%(80名中2館 ) |
2年の間にインターネットが図書館に浸透してきたことがわかります。
4-1.自己研修と情報収集 ↑
4-1-1.情報を探して使う ↑
-
インターネットでの情報を探すには検索エンジンがよく使われる
鈴木尚志. WWWにおけるHTMLファイルリンク. 情報の科学と技術. Vol.48,
no.12, p.768-683(1998.12) <http://www2s.biglobe.ne.jp/~winghead/>
日経マルチメディアの「インターネット・アクティブ・ユーザー調査」 <http://www1.nikkeibp.co.jp/NMM/index.html> 「よくアクセスするホームページ」「ホームページの見つけ方」
サイバースペース・ジャパン(株)の「WWW利用者調査アンケート」 <http://www.csj.co.jp/www7/index.html> 「インターネット利用の目的」
-
よく使うページのリンク集を、ブラウザーを立ち上げたときの最初のページに設定
-
ホームページ「図書館員のためのインターネット」の作成
-
電子メールで連絡をとる
-
MLで情報を交換する
-
電子雑誌で最新動向を把握する
-
コミュニティーを形成する:コミュニケーションを妨げる障壁を取り除き、物流、サービス、思想の交流を促進する。
-
serialst-j(シリアルスト・ジェイ)の運営
-
研究会や飲み会を活性化する
4-1-2.自宅のネットワーク環境の整備 ↑
-
Biglobe(NEC);2,000円/月
-
電話代NTT;1,500円/月
-
プロバイダのホームページサービス
-
ジオシティー社の無料ホームページ
-
DNS社の無料ML
【参考文献3】
4-2.設置母体や図書館の基盤整備 ↑
図書館におけるインターネットの活用レベルをチェックリストにより点検する。
4-2-1.アクセス ↑
-
キャンパス・会社・庁舎にLANが敷設されていて、インターネットに接続している。
-
職員用のハードウェアは2人につき1台以上が用意されている。
-
図書館に利用者用のインターネット端末を設置している。
-
職場に自宅からのアクセスが可能である。
4-2-2.管 理 ↑
-
ネットワークの維持・管理のための要員、組織、予算が確保されている。
-
図書館組織、業務処理手順、資料の運用規則などの改定に着手している。
-
設置母体と図書館とのネットワーク政策の調整ができている。
-
館種による協議会などで共同サーバーの設置している。
-
館員と利用者に対して情報活用能力の育成支援をしている。
-
ハード:汎用機、UNIX、NT、PC、IBM互換機
-
OS:UNIX、Windows、Mac、Linux
-
かな漢字変換:ATOK
-
アプリケーション:ワープロ、表計算、ブラウザ、HTML、画像、メーラー
-
操作:ウインドウ、カット&ペースト、ファイル構造・形式、ネットワーク
-
各種設定:インスツール、カスタマイズ
-
文書作成、プレゼンテーション
4-2-3.サービス内容 ↑
-
図書館からネットワーク情報資源を利用でき、参考業務にも活用している。
-
OPACを公開して、目録の遡及入力が進行している。
-
図書館のホームページを公開し、パブリック系職員が内容を更新している。
-
有料の外部データベースを課金しないで提供している。
-
資料の電子化を進めている。
-
対話型のサーバーを運用していて、ホームページにより、参考質問や資料の予約の受付ができる。
-
インターネットの機能のほとんどを開放している。
4-3.図書館員にとって有用なサイト ↑
4-3-1.インターネットにおける情報検索の有効活用 ↑
-
ディレクトリサービス:サイト単位でを探す
-
検索エンジン:個々のページを探す
-
ネットサーフィン:関連サイトをたどる
-
リンク集:関連サイトをまとめて探す
-
専門サイト:主題専門の企業団体のサイトから探す
-
商用のWeb版DB
-
キーワード変える:区切る、減らす、別の言葉に代える、揺らぎを考慮(ひらがな、カタカナ、漢字、全角、半角、大文字、小文字):検索エンジンの検索方式やホームページ作成者の言葉使いの差がでる
-
検索エンジンを変える:全てのサイトを収録していない
-
リンク集や専門サイトからたどる:検索エンジンの対象外のサイトもある
-
情報の有無の勘を働かせるあきらめる:インターネット上に存在しない情報もある
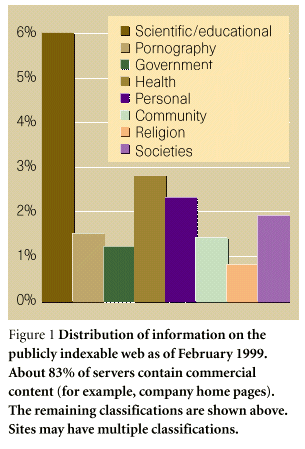
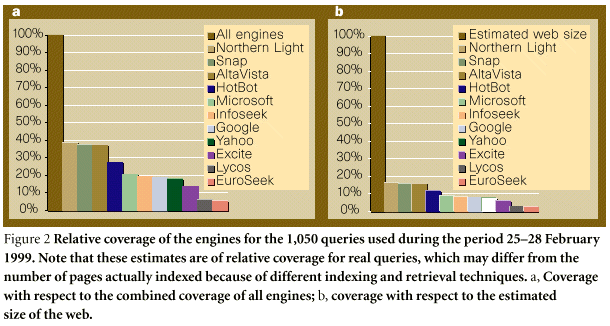
-
Web上の情報は83%が商業的内容で、氾濫しているといわれているポルノは、わずかに1.5%、科学や教育的な内容が6%となっている。
-
検索対象にすることが可能なページが、Web上には推定8億ページ存在する。
-
新しいページが検索エンジンに掲載されるまでには何カ月もかかる。
-
最良のエンジン(Northern Light)でさえ、全インターネットページの6分の1しか網羅していない。
-
AND、OR、NOT、NEAR、前方一致、フレーズ検索
-
検索対象の限定:タイトルのみ、特定URLのみ
-
逆リンク
-
配列:スコア順
-
表示量:簡単な説明文、URL
-
サイトへの取りまとめ:exite
-
ブラウザで表示したページ内の検索:キーワードの存在位置を探す
-
検索結果の保存:録画、HTML形式での保存、PDF形式での保存
-
他国の同一分類へのジャンプ:Yahoo!
-
入力したキーワードの関連語の表示:ALTAVISTAのRefine機能
4-3-2.検索エンジン ↑
-
Yahoo!(ヤフー) <http://www.yahoo.co.jp/> ディレクトリ検索+論理演算 インタビュー:Yahoo!のリンクとしくみ.
情報の科学と技術. Vol.48, no.12, p.704-709(1998.12)
Q:かりんの蜂蜜漬
A:(作 OR 調理) AND (かりん OR カリン OR 花梨) AND (蜂蜜 OR
はちみつ OR ハチ ミツ) NOT (かりんとう OR 酒)
Q:全国の日本酒の蔵元のリストや酒に関するリンク集
A:(日本酒 OR 清酒) AND 蔵元 NOT (洋酒 OR 中国 OR 世界)、「優先する」キーワードを「一覧」と「リンク集」に設定
Q:Agenda(イギリスの雑誌)に載ったW.D.Snodgrassの詩"The Starry
Night"についての論評の掲載号を知りたい。
A:AitaVist +agenda +snodgrass +"Starry Night" →Between
the Lines - Philip Hoy http://www.pbk.co.uk/btl/hoy.htm
検索の視点:目次(20P)
Web情報やWeb検索に関するコラム、1996年1月から現在まで
19 ホームページのホンモノとニセモノ 1999.7.8
18 ドメイン移行で検索サイトは使えるか 1999.3.24
17 サーチサイト競争からポータルサイト競争へ 1998.7.15
16 桜、さくら、サクラ、桜の名所とフレーズ処理 1998.4.8
15 goo,InfoNavigator,infoseekJの総合比較 1998.2.11
14 ロボット系サーチエンジンの重複調査 1997.8.14
13 gooグー:本格的な日本語検索サービスの登場 1997.3.7
12 Yahoo! Japan:日米Yahoo!の相異 1997.2.20
11 HotBot 対 AltaVista 1996.11.24
10 Infoseekのバージョンアップ 1996.11.18
9 検索可能性をあらわす検索力について 1996.9.16
8 Web情報量の日米比較 1996.8.24
7 5,000万クラス一番乗りExciteの実力 1996.7.19
6 サーチエンジンって何ですか 1996.7.12
5 HotBot:検索数で Alta Vista を抜く 1996.5.25
4 登録情報だけでよいのか? 1996.4.11
3 新陳代謝の激しいWeb情報は更新型 1996.2.23
2 分野別新着Web情報 1996.2.9
1 日本のWeb情報は半年で4倍? 1996.1.28
4-3-3.文献検索 ↑
4-3-4.各種DB ↑
-
Yahoo!路線情報「駅すぱーと」 <http://transit.yahoo.co.jp/> インターネットへの入り口奪え「ポータル」目指し大競争.
日経マルチメディア. 1998年9月号 p.66-71 検索サービス会社は,インターネットのトラフィックを集約させることで,広告効果を高めたり,EC(電子商取引)の仲介サービスへのビジネス展開をはかろうとしている.ブラウザメーカー,プロバイダ,コンテンツ会社も,インターネットビジネス全体を再編する「ポータル(門,入り口)」サービスに競って参入してきている.
-
NKB えきから時刻表 <http://eki.joy.ne.jp/>
4-3-5.図書館関連・リンク集 ↑
4-3-6.インターネット関連 ↑
4-3-7.電子雑誌 ↑
【参考文献4】 文献 #01-#08 は必携!!
-
01 『インターネット検索の技とコツ』(宝島社, 1999)
-
02 検索の達人 : 週末のインターネット / 村上晶, 村上弘子著. - 東京
:NECクリエイティブ ,1999.4. - 223p (007.5-M) ブラウザーの設定についても解説。
-
03 アリアドネ. 思考のためのインターネット. ちくま新書, 1999年 文科系800サイトを紹介 <http://ariadne.ne.jp>
-
04 エ・ビスコム・テック・ラボ. 検索エンジン読本. (株)ビー.エヌ.エヌ,
1998.2. 個々の検索エンジンの使い方を詳しく解説している。
-
05 鈴木尚志. 検索エンジン徹底活用法:見たいページへ誰よりも速く.
日本経済新聞社, 1998.2. 例題を使ってキーワードや情報検索サービスの選び方などを解説している。<http://www2s.biglobe.ne.jp/~winghead/>
-
06 サーチエンジン徹底活用術 / 原田昌紀著. - 東京 : オーム社 ,1997.12.
250p(007.63-H)
-
07 インターネット「超」活用法 / 野口悠紀雄著. - 東京 : 講談社 , 1999.4.
- 237p (0073.-N)
-
08 インターネット探検 / 立花隆著. - 東京 : 講談社 , 1996.4. - 189p
(007.3-T)
-
09 インターネットで文献検索 改訂版 / 実践女子大学図書館編集 1999
-
10 文科系のための情報検索入門 : パソコンで「漱石」にたどりつく / 安永尚志著
; 国文学研究資料館編. - 東京 : 平凡社 , 1996.7. - 256p (007.5-Y)
-
11 戸田愼一;影浦峡;海野敏. インターネットで情報探索. 日外アソシエーツ,
1994.11, 243p.
-
12 連載:インターネット活用術. 情報の科学と技術. Vol.46, no.1 (1996.1)-
-
13 連載講座:インターネット活用法. 情報管理. Vol.39, no.1 (1996.4)-
-
14 インターネット活用術 / 奥乃博著. - 東京 : 岩波書店 , 1996.11. - vii,
112p (007.3-O)
-
15 インターネット時代の情報探索術 / 大串夏身著. 青弓社 , 1997.3. - 175p(007.3-O)
-
16 学術情報収集テクニック : インターネットから文献検索・整理まで / 祝部大輔編
; 日地康武 [ほか]共著. - 東京 : 薬業時報社 , 1995.10. - xi, 265p (018.49-G)
-
17 情報検索のためのインターネット活用術 / 情報科学技術協会編. - 東京 :
日外アソシエーツ. - 東京 : 紀伊国屋書店 (発売) , 1996.9. - 218p (007.3-J)
-
18 データベース活用マニュアル : 情報検索、パソコン通信、インターネット…ビギナーからサーチャーまで.
- 東京 :情報図書館RUKIT. - 東京 : 紀伊国屋書店 (発売) , 1996.10. - v, 266p
(007.5-D)
-
19 インターネット情報収集術 / 水谷哲也,佐々木篤著. - 東京 : 秀和システム
, 1997.2. - 223p (007.3-M)
-
20 アリアドネ. 調査のためのインターネット. ちくま新書, 1996年
|
4-4.インターネットの課題 ↑
4-4-1.図書館にとってのインターネット ↑
-
種類:情報検索サービス、電子図書館、電子出版、生活・娯楽情報
-
対応:基盤整備、予算措置、課金、利用指導
-
種類:ホームページ、OPAC、電子図書館、地域・生活情報
-
対応:基盤整備、予算措置、職員研修、業務体制
-
種類:電子メール、メーリングリスト(ML)、チャット、掲示板
-
対応:業務への応用
4-4-2.インターネットにとっての図書館 ↑
-
設置母体や出版社などと協力して、コンテンツを作り出せるか?
-
コンテンツに構造をもたせることができるか?:ホームページの組織化
-
メタデータ
-
Field 856
-
電子文献の引用法
-
組織化~配信・提供
-
奥付(作成者の連絡先、更新日など)の必要性
-
作成者の必須情報の欠如:地図、交通、職員名簿
-
インターネット上のコンテンツへのアクセスを、広く保証する義務がある。
-
コミュニティーへのネットワーク基盤の整備は誰の仕事か?
-
設置母体は、回線を整備する。
-
図書館は、パソコンを設置し、利用指導を行う。
-
個人的な利用は、個人でプロバイダと契約する。
4-4-3.図書館とインターネット ↑
-
図書館は、インターネットを利用者に、どのように提供していくのか?
-
個人レベルの対応にまかす:個人でプロバイダ契約
-
図書館としての対応:インターネット接続したパソコンの公開、図書館ホームページの公開、機器操作と情報検索の利用者教育
-
設置母体の対応にあわせる:自治体・大学によるネットワーク環境整備
-
図書館は、インターネットを業務に、どのように利用していくのか?
-
職員レベル:個人でプロバイダ契約
-
単館レベル:職員に1台のパソコン
-
コンソーシアムのレベル:システムの共同利用
-
図書館は、設置母体やインターネット社会と、どのようにつきあっていくのか?
-
業務のツールとして情報機器・情報検索・ネットワークを使いこなす
4-4-4.問題点 ↑
-
情報基盤の整備状況や、情報政策に大きなばらつきがあり、ユーザー格差や図書館格差が拡大している。この格差は、紙媒体の時代の格差を引き継いだものであり、よい図書館はますますよくなり、悪い図書館はますます悪くなる。
-
基本的な考え方が理解されていない。
-
市民や学生に情報が与えられるのは当たり前であり、自治体や大学には情報を提供する義務がある。
-
インターネットは、必要なときに、必要な人に、必要な情報を、簡単に送り届ける技術である。ホームページには、明と暗(社会レベル)がある。
-
人員削減、予算削減、アイデンティティーの喪失という状況の中で、存在をアピールするために、ネットワークを使った新規事業の展開は有効な手段であり、そのためには、個人の能力開発と組織の管理能力の強化が必要である。ただでさえ様々な問題を抱え込んでいる上に、これ以上の事業展開が可能か疑問は残るものの、やらなければ図書館以外のどこかがやってしまう。
-
図書館のアイデンティティーや館種による環境とユーザー特性の相違が存在する。
-
公共図書館:生涯学習→ 地域住民
-
大学図書館:大学改革、次期システム → 教職員、学生
-
学校図書館:100校プロジェクト → 生徒
-
専門図書館:日本経済→ 従業員
【参考文献5】
-
W.F.バーゾール著; 根本彰ほか訳. 電子図書館の神話. 勁草書房, 1996.4,
254p. 電子図書館の隆盛により従来の図書館は衰退するであろうか。否と著者は答える。図書館の存在と図書館員の重要性を再評価する(帯の紹介より)
-
インターネット市民革命 / 岡部一明. 御茶の水書房, 1996.5, 366p. (007.3-O)
-
悦子・ウィルソン著. サンフランシスコ公共図書館限りない挑戦.. JLA, 1995.12.
-
日本図書館学会研究委員会編.. ネットワーク情報資源の可能性(論集・図書館情報学研究の歩み
第15集). 日外アソシエーツ, 1996.1, 187p.
-
東京大学大学院教育研究科図書館情報学研究室主催 公開シンポジウム「公共図書館と電子メディア利用」1999年3月5日(金)10:00~17:00
東京大学教育学部156教室にて レジュメの全文がここに置いてあります。<http://wolverine.p.u-tokyo.ac.jp/text/PLNG/Symposium.html>
-
岡本薫. 電子図書館と著作権. 情報管理. 42(1) p.18-31 (1999.4)
-
菅谷明子. 進化するニューヨーク公共図書館. 中央公論. 1999年8月号 p.270-281
-
三好万季. 16才歳高校生の緊急提言 全中高生に無料でパソコンを!. 中央公論.
1999年9月号 読売新聞のBit By Bitに関連記事 <http://www.yomiuri.co.jp/bitbybit/bbb07/981103.htm>
-
川崎良孝. フィルターソフトとアメリカ図書館協会. 図書館界. 51(3) p.126-139
(1999.9)
-
森山光良. わが国の公共図書館の都道府県域総合目録ネットワークに関する考察--目録データ処理方式を中心に--.
図書館学会年報. 45(1) p.17-34 (1999.9)
-
林紘一郎; 田川義博. ユニバーサルサービス:マルチメディア時代の「公正」.
中央公論社, 1994.3, 224p. (中公新書 1175)
-
青山南. 華氏四五一のサンフランシスコ. 本の雑誌. No.165, p.32-33 (1997.3)
-
サイバー時代の図書館の「使命」:コンピュータ端末をずらりと並べても、蔵書が減っては意味がない?.
ニューズウイーク日本版. Vol.11, no.4, p.76-79 (1996.10.30)
-
インターネットと図書館の未来--ネットワーク環境における新たな戦略--(第43回日本図書館学会研究大会シンポジウム記録).
図書館学会年報. Vol.42, no.1, p.63-82 (1996.3)
-
西垣通. インターネットで共同体は崩れるのか. 世界. No.622, p.291-304 (1996.5)
-
特集:インターネット日本への衝撃. 世界. No.623, p.27-69 (1996.6)
-
クリフォード・ストール著; 倉骨彰訳. インターネットはからっぽの洞窟. 草思社,
1997.2.
-
岡部一明. 市民メディアとしてのインターネット:ネーダーグループのラブ氏を日本に呼んで.
グラフィケーション(ゼロックスの広報誌). No.88, p.19-21 (1996)
-
岡部一明. 情報化時代に市民にアクセスを保証する図書館:カリフォルニア大学図書館,サンフランシスコ市立中央図書館.
情報の科学と技術. Vol.47, no.3, p.136-142 (1997.3) [特集:情報化意識の変革--地域,市民ベルの情報化]
-
辻由美(つじ・ゆみ)著 図書館であそぼう:知的発見のすすめ219p (講談社現代新書1453
) 1999.05 http://www.trc.co.jp/trc/book/book.idc?JLA=99022154
-
森山光良. わが国の公共図書館の都道府県域総合目録ネットワークに関する考察-目録データ処理方式を中心に-.
日本図書館情報学会誌.Vol.45, No.1, March, 1999(通巻137号)p.17-
-
岡本薫(文化庁国際著作権室長). 社会教育関係者のためのマルチメディア時代の著作権:「人権」を守るために.
全日本社会教育連合会. 1997.9, 139p. ISBN:4-7937-0103-5 概要については、「わかりやすく著作権の基礎を理解できる最適本」<http://www2d.biglobe.ne.jp/~st886ngw/diary/diary1003.htm#bm1>
|
5.インターネットを使った情報検索演習 ↑
注意:検索エンジンでの検索結果を表示するときには、開きたいリンクにマウスのポインターをあわせて右クリックし、「新しいウインドウを開く」を選択して、新しいブラウザーを立ち上げる。
◆例題0◆ ↑
Q1:インターネットの歴史、インターネットの仕組み、インターネットの使い方について。
A1:Yahoo!<http://www.yahoo.co.jp/>でカテゴリーとして存在するキーワードの「インターネット講座」で検索 <http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%A5%A4%A5%F3%A5%BF%A1%BC%A5%CD%A5%C3%A5%C8%B9%D6%BA%C2>。「地域情報:日本の地方:近畿:大阪:教育:大学:大阪市立大学:イベント:インターネット講座」がみつかる。「インターネット概論」学術情報センター:中野秀男教授<http://hosp.msic.med.osaka-cu.ac.jp/koho/vuniv97/lectnaka.htm>がよさそうである。
Q2:アメリカ民謡である「峠の我が家」の歌詞と曲を知りたい。
A2:Yahoo!<http://www.yahoo.co.jp/>でカテゴリーとして存在するキーワードの「歌詞」で検索。カテゴリーの「エンターテインメント:音楽:歌詞」<http://www.yahoo.co.jp/Entertainment/Music/Lyrics/>がある。「World
Folk Song」<http://webclub.kcom.ne.jp/mb/folksong/index.html>でみつかる。
Q3:検索エンジンの守備範囲やポルノの割合に関する記事を探す。
A3:goo<http://goo.ne.jp/>を「検索エンジン 守備範囲 ポルノ 割合」で検索。「ZDNN:
Webは氷山。ポルノは1.5%,検索エンジン守備範囲は16%」<http://www.zdnet.co.jp/news/9907/08/necri.html>がみつかる。
CNET<http://japan.cnet.com/>かZDnet<http://www.zdnet.co.jp/>など。
◆例題1◆第2回検索の鉄人 第一次予選・ラウンド2 1998年6月19日~6月25日 ↑
-
アニメ「ムーミン」を日本で最初にオンエアーしたテレビ局は?
-
今日認められている能の演目のうち、最も古いとされ、五穀豊穰などを祝う神聖な演目とは何?(漢字一文字で)
-
ラクロスのゴールは、タテ、ヨコ、奥行きともに同じ長さです。内側から計った場合、一辺の長さは何メートルでしょう? ○1.83メートル
○2.74メートル ○2.86メートル ○3.22メートル
-
プロレスラー、初代「タイガーマスク」がデビューしたのは、西暦でいうと何年のこと?(アニメの世界の出来事ではありません)
-
710年に遷都された日本の都にあって、その宮殿の南に位置し、つい先頃復元工事が完成した門の名は?
-
日本初の切手をデザインした人物は誰? [難問!]
-
次に挙げる魚のうち、卵から生まれないものはどれ? ○シロギス ○ライギョ
○ウミタナゴ ○アイナメ [難問!]
-
アメリカの独立宣言が起草されたことで有名な都市があります。1976年、この都市の、あるホテルで大量発生した病気の病原体は、何菌?
-
江戸時代の三大改革。このうち、今でいう「宝くじ」を禁止したのはどれ? ○享保の改革
○寛政の改革 ○天保の改革
-
シクラメンには、和名があります。その由来になった「ある一言」を発した歌人の名は? [難問!]
【回答】
| 1)フジテレビ 2)翁[順番に丹念に読む] 3)1.83メートル 4)1981年 5)朱雀門 6)松田敦朝
または 松田玄々堂[切手 AND 最初 AND (デザイン OR 図案 OR 図柄 OR 意匠)] 7)ウミタナゴ[「卵を生む」魚を検索して選択肢をつぶしていく、胎生というキーワードを使う] 8)レジオネラ菌 9)天保の改革[(享保の改革
OR 寛政の改革 OR 天保の改革) AND 宝くじ] 10)九条武子[和名の表現の違いがある] |
◆例題2◆第2回検索の鉄人 第一次予選・ラウンド4 1998年7月3日から7月9日 ↑
-
明治大正時代に活躍した青い目の落語家、快楽亭ブラック。彼が出生したオーストラリアの都市名は?
-
明治時代にお目見えした日本初の水族館は、ある動物園の園内に設置されました。この動物園とは?
-
プロ野球界の偉大な選手が参加している「名球会」。今年の5月末現在、会員のうちピッチャー出身は何人?
-
川島なお美も受験するというソムリエ資格認定試験。一般の人が受ける場合、その受験料はいくら?
○6,000円 ○12,000円 ○19,000円 ○20,000円
-
国民の祝日「海の日」。その前身であった記念日を提案した、当時の大臣の氏名は?
-
国際機関の略称のこと。「IMF」は国際通貨基金、「ILO」は国際労働機関、では、「IFC」と言えば?
-
人間の涙の膜は3つの層からできています。一番内側の層の名前は?
-
原子力発電で使用される、ウランとプルトニウムを混合して作られる燃料のことをアルファベット3文字で何という?
(半角で)
-
金の製錬法のひとつで、水、鉛、灰を使った方法のことを何という?(全角日本語で)
-
旧日本海軍の戦艦大和。その主砲の口径(筒の直径)は何センチ? ○36センチ
○40センチ ○45センチ ○46センチ
【回答】
| 1)アデレード 2)上野動物園 3)14人[名球会の公式サイト] 4)12,000円[キーワードを途中で区切る] 5)村田省蔵 6)国際金融公社[IMF
国際通貨基金 ILO 国際労働機関 IFC] 7)ムチン層[検索結果リストをじっくり眺めて、法人のページ「参天製薬-涙の話」へ] 8)MOX 9)灰吹法 10)46センチ[「戦艦大和
AND 主砲 NOT IRONBOTTOM」で関係のないサイトを除く] |
◆例題3◆各県のインターネットの状況を調べる ↑
参加者名簿の番号の県と、自分の好みの県を比較して、ホームページの構成や発信情報の内容をチェックする。
Q1:県のネットワーク政策はどうなっているか?
Q2:県のネットワークの名称は?
Q3:県のページから、図書館へのリンクや図書館の案内へのリンクはあるか?
Q4:図書館に関する情報はどの程度まで公開されているか?
Q5:図書館のホームページはどうなっているか?
Q6:OPACはあるか? 収録点数は? 検索の手引きはわかりやすいか?
Q7:その県の有名な人物(歴史的、芸能人など)の詳細情報を、検索エンジンで探す。
Q8:次の8冊の図書を全て所蔵している図書館はどこか?
TRC日本国内の図書館 <http://www.trc.co.jp/trc-japa/guide/library.htm> などからはじめる。
『インターネット検索の技とコツ』(宝島社, 1999)
検索の達人 : 週末のインターネット / 村上晶, 村上弘子著. - 東京 :NECクリエイティブ
,1999.4.
アリアドネ. 思考のためのインターネット. ちくま新書, 1999年
エ・ビスコム・テック・ラボ. 検索エンジン読本. (株)ビー.エヌ.エヌ,
1998.2.
鈴木尚志. 検索エンジン徹底活用法:見たいページへ誰よりも速く. 日本経済新聞社,
1998.2.
サーチエンジン徹底活用術 / 原田昌紀著. - 東京 : オーム社 ,1997.12.
インターネット「超」活用法 / 野口悠紀雄著. - 東京 : 講談社 , 1999.4.
インターネット探検 / 立花隆著. - 東京 : 講談社 , 1996.4. - 189p
◆例題4◆図書や雑誌の所蔵 ↑
-
図書「Cronin, Mary J.(ボストン大学図書館);黒川利明監訳. インターネット
: ビジネス活用の最前線. インターナショナル・トムソン・パブリッシング・ジャパン,
1994.10」の所蔵館は?
-
雑誌「ASCII(アスキー出版)」1994年9月号の所蔵館は?
-
『インターネット検索の技とコツ』(宝島社, 1999)の所蔵館は?
-
図書「鈴木尚志. 検索エンジン徹底活用法:見たいページへ誰よりも速く. 日本経済新聞社,
1998.2.」の簡単な内容紹介を知りたい。
-
米国の新聞のNew York Timesの1945年を見たいが、東京周辺の図書館を紹介してほしい。
-
Thornton WilderのHeaven’s My Destination (1930年代)“我が行く先は天国”の翻訳はあるか。
-
大草原の小さな家の原書をみたい。
-
「アファール猿人」別名ルーシーの「直立歩行」について最近出た本は。
-
日本アイヒェンドルフ協会の雑誌は何という雑誌で、どうやって入手できるか。
-
『大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録』CD-ROM版の値段を知りたい。
◆例題5◆事項調査 ↑
-
TLOとは何か?
-
エコプロジェクトの概要について知りたい。
-
Gショックの歴史や製品情報について知りたい。
-
英国図書館の日本語の概要はあるか。
-
演劇集団Dump type(ダムタイプ)とT.Furuhashi(古橋悌二)について知りたい。
-
インターネット入試を行っている大学のリストがほしい。
-
青い雨蛙について知りたい。
-
横浜市の高等学校の偏差値を知りたい。
-
DHCPとは。インターネット関連の用語らしい。
-
図書館関係のメーリングリストにはどのようなものがあり、どのような議論がされているのか。
-
「図書館の情報化の必要性とその推進方策について--地域の情報化推進拠点として(報告)平成10(1998)年10月27日 生涯学習審議会社会」<http://www.monbu.go.jp/singi/syogai/00000227/>をめぐる動きを知りたい。
◆例題6◆特定サイトからの検索 ↑
-
「江ノ島」の出てくる古典籍には何があるか。
-
「松浦宮」の出てくる古典籍には何があるか。
-
東京駅からの秋田新幹線「こまち」の始発時間は。角館駅までの所要時間とルートは。
-
京浜鶴見駅から東京駅までの所要時間とルートは。
-
本屋さんの丸善(株)の従業員数と業績を知りたい。
-
ソニー(株)の従業員数と業績を知りたい。
-
横浜市にある鶴見大学の地図、住所、電話番号を知りたい。
-
宮城大学の地図、住所、電話番号を知りたい。
-
1997年の消費者物価指数と数年間の傾向を知りたい。
-
平成10年の勤労者世帯の貯蓄現在高の1世帯平均を知りたい。
◆例題7◆全文データの検索 ↑
-
「図書館員の倫理綱領」の全文を見たい。
-
「大学図書館における電子図書館的機能の充実・強化について(建議) 平成8年7月29日
学術審議会」を見たい。
-
「電子出版物の収集・保存・利用と納本制度/納本制度調査会電子出版物部会」を見たい。
-
「根本彰. 地域社会と公共図書館--地方分権の論理を超えて」をみたい。
-
「高度情報通信社会推進本部決定. 高度情報通信社会推進に向けた基本方針」をみたい。
-
地方分権推進委員会の勧告をみたい。
-
著作憲法の前文を見たい。特に電子資料の著作権について知りたい。
-
源氏物語の本文、雨月物語の本文、学問のすすめの本文をみたい。
-
平成11年の人事院の給与勧告の全文を見たい。
-
地方自治法(地方公務員法)第204条の全文を見たい。
◆例題8◆海外の検索 ↑
-
Agenda(イギリスの雑誌)に載ったW.D.Snodgrassの詩"The Starry Night"についての論評の掲載号を知りたい。 A:AitaVist +agenda
+snodgrass +"Starry Night" →Between the Lines - Philip Hoy http://www.pbk.co.uk/btl/hoy.htm
-
17世紀後半に誕生した最初の雑誌、フランスのJournal des Scavans(5 Jan.1665)と英国のPhilosophical
Transactions(6 Mar.1665)をの概要とその表紙をみたい。 フランスのJournal
des Scavans(5 Jan.1665)(創刊号の表紙の画像 <http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/dossitsm/gc189-35.htm>[cited:
1998-11-28]、英国のPhilosophical Transactions(6 Mar.1665)(創刊号の表紙の画像 <http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/dossitsm/gc189-36.htm>[cited:
1998-11-28]、Philosophical Transactions の全文データ(画像) <http://www.bodley.ox.ac.uk/ilej/>
-
Lindau man or Lindou man;リンドーマンに関して知りたい。Lindauはドイツのボーデン湖畔の都市で、質問とは無関係。『ミイラ(ビジュアル博物館)』(同朋舎出版)にリンドウ人として写真と概要が掲載。1984年に英国チェシャー州リンドウモスの泥炭地で見つかった約2,300年前の死体。ピート・マーシュ(泥炭沼)というニックネームをつけられて有名になった。
◆例題9◆検索困難な事例 ↑
-
北緯40度40分、西経70度37分は陸か、海か。
-
小林やすのぶ編纂 東京切絵図 中島くまじろう出版 は全何枚か。
-
東と西の文学[東と西の文学の会] 7号 1987 瀬川裕司 救世主は如何にして緩慢に死ぬか--G・グラス「猫と鼠」試論--を取り寄せたい。
-
大阪遊技史学会の住所と電話番号を知りたい。
-
再来年の春分の日と秋分の日はいつか。
-
幕末の日本の大砲の絵を見たい。
-
1700年代の英国の女性の相続税の概要について知りたい。
-
WEGAの開発戦略などについて知りたい。
-
ダイオキシンについて知りたい。
-
コンビニの商品仕入れの仕組みや、陳列方法について知りたい。
(資料1)図書館における電子化、情報化の背景 ↑
高度情報通信社会推進に向けた基本方針 平成10年11月9日 高度情報通信社会推進本部決定 ↑
【<http://www.kantei.go.jp/jp/it/981110kihon.html>】
【1995.2.21版<http://www.kantei.go.jp/jp/it/990422ho-7.html>の最新版】
|
目次
1.高度情報通信社会に向けた基本的な考え方
(1)高度情報通信社会の意義
(2)高度情報通信社会実現のための行動原則~3つの原則~
[民間主導、政府による環境整備、国際的な合意形成に向けたイニシアティブの発揮]
(3)高度情報通信社会の構築に向けた官民の役割
2.高度情報通信社会の実現に向けた課題と対応
(1)電子商取引等推進のための環境整備
(2)公共分野の情報化
(3)情報通信の高度化のための諸制度の見直し
(4)情報リテラシーの向上、人材育成、教育の情報化
(5)ネットワークインフラの整備
(6)基礎的・先端的な研究開発
(7)ハイテク犯罪対策・セキュリティ対策・プライバシー対策
(8)ソフトウェアの供給
(9)コンテンツの充実
(10)相互運用性・相互接続性の確保
3.国際的なイニシアティブの発揮
(1)電子商取引の制度的・技術的環境整備に向けた国際貢献
(2)世界的な情報通信インフラの構築、相互運用性・相互接続性の確保
(3)共同プロジェクトの実施
(4)ハイテク犯罪対策の推進
4.これからの進め方
(1)当面の目標~4つの目標~
[電子商取引普及、電子的な政府の実現、情報リテラシー向上、情報通信インフラ整備]
(2)関係省庁一体となった本基本方針の早急な実施
(3)フォローアップ
(4)基本方針の見直し |
大学図書館における電子図書館的機能の充実・強化について(建議)平成8年7月29日
学術審議会 ↑
【<http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/anul/material/kengi.html>】
|
目次
1.大学図書館における電子図書館的機能の整備の必要性
(1)情報二ーズの増大と多様化
(2)電子的情報資料の増大
(3)資料保存機能の向上
(4)資料の有効利用
(5)情報検索機能の向上
(6)情報発信活動の支援
2.電子図書館的機能の整備の基本的考え方
(1)整備のためのビジョン策定
(2)学内関連組織と連携協力の推進
(3)大学図書館間の連携・協力の強化及ぴ相互運用性の確保
(4)教育活動への配慮
(5)著作権の保護,セキュリティの確保及ぴプライバシーの保護
3.電子図書館的機能の整備の方策
(1)資料の電子化の推進
1)目録情報の電子入力の促進
2)資料電子化の段階的・継続的な取組
3)資料電子化の効率的な実施
4)電子化資料作成の支援
(2)施設・設備の整備
(3)研究開発の推進
(4)組織体制の整備
(5)図書館職員の研修の充実
(6)情報リテラシー教育への支援
(7)著作権への対応
4.電子図書館プロジェクトの推進等 |
図書館の情報化の必要性とその推進方策について--地域の情報化推進拠点として(報告) ↑
平成10(1998)年10月27日 生涯学習審議会社会教育文化審議会計画部会図書館専門委員会【図書館雑誌.
92(11) p.1032-1037 (1998.11)に掲載】
【『資料5:公共図書館の新しい情報サービスについて(調査結果)/文部省生涯学習局学習情報課
平成10年8月1日現在』は、図書館雑誌. 93(2) p.130-135 (1999.2)に掲載】
<http://www.monbu.go.jp/singi/syogai/00000227/>
|
目次
1.現状
(1)資料の電子化の動向
(2)情報通信技術を利用した新しい図書館サービス
①コンピュータ等の導入状況
②有料のオンラインデータベースの利用
③インターネット接続コンピュータの利用者への開放
④自館からの情報発信(ホームページ上で所蔵情報の検索が可能な館)
⑤新しい情報サービスに対する職員の研修
2.今後の課題
(1)図書館の新しい役割
①地域の情報拠点としての図書館
②地域住民の情報活用能力の育成支援
(2)具体的な推進方策
①情報通信基盤の整備
ア.コンピュータの設置
イ.インターネット等の利用
ウ.CD-ROM等の活用
エ.衛星通信システムの活用
オ.TV会議システムの活用
②資料の電子化の利点とその活用
③司書等の研修及び住民の情報活用能力育成
④著作権、肖像権等を保護する体制
3.提言
(1)地域における図書館と情報通信基盤の整備
(2)地地域電子図書館構想
(3)司書の研修の充実
(4)住民の情報活用能力の育成
(5)図書館サービスの多様化・高度化と負担の在り方
(6)インターネット接続に係る通信料金等の負担の軽減 |
薬袋秀樹. 公立図書館における電子情報の導入に関する論議について. 図書館雑誌.
93(6) 1999.6 以下の記事についての交通整理をしている。
1)「小特集 (2)図書館の無料原則を考える:電子情報の利用」『図書館雑誌』93,1999.2,p.121-128.
2)「特集 無料の原則と「電子化資料」の導入について」『みんなの図書館』260,1998.12,p.1-25.
3)図書館問題研究会常任委員会「生涯学習審議会社会教育分科審議会計画部会図書館専門委員会報告(「図書館の情報化の必要性とその推進方策について」)に対する見解」『みんなの図書館』263,1999.3,p.71-73.
4)「特集 電子資料の導入を進めよう」『みんなの図書館』265,1999.5,p.1-50.
5)生涯学習審議会社会教育分科審議会計画部会図書館専門委員会「図書館の情報化の必要性とその推進方策について?地域の情報化推進拠点として?(報告)」『図書館雑誌』92,1998.11,p.1032-1037.
6)糸賀雅児「図書館専門委員会『報告』の趣旨と<無料原則>」『図書館雑誌』92,1998.12,p.1097-1099.
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について(答申)(平成10年7月29日
教育課程審議会) ↑
<http://www.monbu.go.jp/singi/katei/00000216/#1-4>
|
目次
前 文
I 教育課程の基準の改善の方針
1 教育課程の基準の改善の基本的考え方
(1)教育課程の基準の改善に当たっての基本的考え方
(2)教育課程の基準の改善のねらい
(3)各学校段階・各教科等を通じる主な課題に関する基本的考え方
(道徳教育)
(国際化への対応)
(情報化への対応)
(環境問題への対応)
(少子高齢社会への対応等)
(横断的・総合的な学習、教育課程の基準の大綱化・弾力化)
2 各学校段階等を通じる教育課程の編成及び授業時数等の枠組み
(1)教育課程の編成
(2)「総合的な学習の時間」
(3)授業時数の基本的な考え方等
ア 年間総授業時数
イ 小学校、中学校、高等学校等の年間授業週数
ウ 小学校、中学校、高等学校等の授業の1単位時間
3 各学校段階等ごとの教育課程の編成及び授業時数等
(1)幼稚園の教育課程の編成及び教育時間等
(2)小学校の各教科の編成及び年間授業時数
(3)中学校の各教科の編成及び年間授業時数
(4)高等学校の各教科・科目の編成、必修の各教科・科目の単位数、
卒業に必要な各教科・科目の修得総単位数等
(5)盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の編成と年間授業時数等
(6)中高一貫教育の教育課程の編成等
4 各教科・科目等の内容
(1)幼稚園
(2)小学校、中学校及び高等学校
i)国語
ii)社会、地理歴史、公民
iii)算数、数学
iv)理科
v)生活
vi)音楽、芸術(音楽)
vii)図画工作、美術、芸術(美術、工芸)
viii)芸術(書道)
ix)家庭、技術・家庭
x)体育、保健体育
xi)外国語
xii)情報
xiii)専門教育に関する各教科・科目
ア 職業に関する各教科・科目
(ア)家庭
(イ)農業
(ウ)工業
(エ)商業
(オ)水産
(カ)看護
(キ)福祉
(ク)情報
イ その他の専門教育に関する各教科・科目
xiv)道徳教育
xv)特別活動
(3)盲学校、聾学校及び養護学校
II 教育課程の基準の改善の関連事項
1 教科書及び補助教材
2 指導方法
3 学習の評価
4 大学、高等学校など上級学校の入学者選抜
5 教師
6 学校運営
7 家庭及び地域社会における教育との連携
別表1 小学校の各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の年間標準授業時数
別表2 中学校の各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の年間標準授業時数
別表3 高等学校の各教科・科目及び標準単位数 |
(情報化への対応)では「2003年度までにすべての学校がインターネットに接続できるよう計画的な整備を行なうのにともなって、小学校、中学校及び高等学校を通じ一貫した系統的な情報教育が行なえるように関係教科等の改善充実を図り、コンピュータや情報通信ネットワーク等を含め情報手段を活用できる基礎的な資質や能力を培う必要があるとしている。
学校段階ごとには、小学校においては「総合的な学習の時間」をはじめ各教科などの様々な時間でコンピュータ等を適切に活用することを通じて情報化に対応する教育を展開する。中学校においては技術・家庭科の中でコンピュータの基礎的な活用技術の習得など情報に関する基礎的内容を必修とし、高等学校においては、情報手段の活用を図りながら情報を適切に判断・分析するための知識・技能を習得させ、情報社会に主体的に対応する態度を育てることなどを内容とする教科「情報」を新設し必修とすることが適当である」としている。ネットワークからの情報の取り出し方、ネットワークへの情報発信のやり方、ネットワーク上の情報の取り扱い方などを総合的に学んで行く。
2003年度から高校で新教科「情報」が必修に<http://www.monbu.go.jp/series/00000051/>なることに伴い、「普通教科『情報』試作教科書(仮称)/情報処理学会初等中等情報教育委員会ワーキング・グループ」なども試作されている。
情報A:http://www.ics.teikyo-u.ac.jp/InformationStudy/ahtml/index.html
情報B:http://www.ics.teikyo-u.ac.jp/InformationStudy/bhtml/index.html
情報C:http://www.ics.teikyo-u.ac.jp/InformationStudy/chtml/index.html
(資料2)情報リテラシー:パソコンとインターネット ↑
1.パソコンの操作 ↑
1-1.オペレーションシステム:Windows ↑
1-1-1.キー操作 ↑
| |
SHIFT + → |
「範囲選択」 |
| |
CTRL + C |
選択範囲の「コピー」 |
| |
CTRL + X |
選択範囲の「切り取り」 |
| |
CTRL + V |
コピー、切り取り部分の「張り付け」 |
| |
CTRL + Z |
操作を「元に戻す」 |
| |
HOME CLR |
「行頭」へカーソル移動 |
| |
HELP |
「行末」へカーソル移動 |
| |
CTRL + HOME CLR |
「文頭」へカーソル移動 |
| |
CTRL + HELP |
「文末」へカーソル移動 |
| |
ROLL UP
ROLL DOWN |
画面「スクロール」 |
| |
CTRL + COPY |
アクティブ「画面コピー」 |
| |
F4 |
直前動作の「繰り返し」 |
| |
CTRL + F6 |
「文章切り替え」 |
| |
CTRL + TAB |
「ウィンドウ切り替え」、タスクバーに複数ウィンドウを表示 |
| |
組み合わせ |
選択 + 移動, コピー + 切り替え etc |
| |
左クリック |
選択 |
| |
左ダブルクリック |
実行 |
| |
右クリック |
機能のプルダウン |
1-1-2.日本語入力:ATOK ↑
| |
入力 |
入力中の修正 |
| |
変換 |
部分変換
変換中の修正 |
| |
確定 |
部分確定
確定後の修正 |
| |
変換中のキー |
space 変換
F7 全角カタカナ
F8 半角カタカナ
F9 全角英数字
F10 半角英数字
SIFT + space 半角スペース |
1-1-3.エクスプローラー ↑
| |
階層 |
ディスク、フォルダー、ファイル |
| |
ファイル操作 |
開く、コピー/カット/ペースト |
| |
ネットワーク |
ディスク、ファイル、プリンタの共有 |
1-2.アプリケーション ↑
1-2.1.ワープロ:Word ↑
| |
書式の設定 |
スタイルと書式、テンプレート |
| |
文章の構成 |
アウトラインモードなど、表 |
| |
他アプリの利用 |
他のアプリケーションからの張り付け、挿入 |
| |
印刷 |
ページ設定、文字数/行数 |
| |
キー操作 |
Windowsに準じる
(元に戻した操作を「やり直す」) |
| |
ネットワーク |
ファイルとプリンタの共有 |
| |
|
|
1-2-2.表計算:Excel ↑
| |
入力 |
セル、行/列、ワークシート、フォルダ |
| |
計算 |
=1239*1234 計算
=P7+Q7 セルの計算
=SUM(F8:F15) 合計
=ROUNDDOWN(Q719*1.05,0) 四捨五入
=CONCATENATE(A10,"-",C10) 文字列結合 |
| |
データ操作 |
ソート、集計、グラフ |
| |
印刷 |
行タイトル、見出し、縮小 |
1-2-3.通信ソフト:秀Term ↑
| |
パソコン通信 |
学情メール |
| |
オンライン検索 |
NACSIS-IR |
| |
telnet |
鶴見大opacなど |
1-2-4.画像編集:Paint Shop ↑
| |
画像ファイル |
BMP、GIF、JPG |
| |
他アプリへの利用 |
Wordへの張り付け |
| |
画像加工 |
拡大/縮小、ファイル形式変換、画像取り込み |
1-2-5.ブラウザ:Netscape ↑
| |
各部分の機能 |
-
タイトルバー 現在の画面のタイトル
-
メニューバー 機能、設定を呼び出すためのメニューブック・マーク、印刷、セーブ、画像/動画/音声を再生するためのヘルパーアプリケーションなどを設定する。
-
ツールバー よく使う機能のアイコン
-
ロケーションフィールド 現在のURL(Uniform Resource Locator)<プロトコル://ホスト/パス>
-
ネットスケープ社のロゴ ネットワークへのアクセス中は星が流れる6)ディレクトリボタン:ネットスケープ社の選んだ情報提供のリソース
-
コンテンツエリア 接続先の情報の中身が表示される
-
セキュリティインジケータ セキュリティの状態を表示。鍵が途中で切れている場合、クレジットカードの暗証番号などを送らないほうがよい。普段は気にしなくともよい。
-
ステータスメッセージフィールド 現在の動作状態を表示リンク先のURL、ネットワーク接続のメッセージ など
-
プログレスバー 接続先からのデータの読込み量を表示
|
| |
データ操作 |
HTMLソース表示、セーブ、ブックマーク、印刷 |
| |
ファイル表示 |
ローカル/ネットワーク、ファイル形式 |
2.インターネットの利用 ↑
2-1.インターネットとは何か ↑
| |
データベース |
サーチエンジン、ディレクトリ、リンク集 |
| |
コミュニケーションツール |
情報交換、情報発信、電子メール |
| |
コミュニティー |
|
2-2.インターネットの仕組み ↑
| |
回線 |
専用線接続、電話回線接続、NSPIXP |
| |
費用 |
通信(回線)、サーバー(ハード)、DB(情報資源) |
| |
技術 |
CGI、Z39.50 |
2-3.電子メール:インターネットはメールに始まりメールに終わる ↑
| |
メーラー |
|
| |
受信/発信 |
|
| |
添付ファイル |
|
| |
メーリングリスト |
|
2-4.WWW ↑
| |
Home Pageの作成 |
HTML、FTP |
| |
Home Pageの評価 |
|
3.ドキュメントの作成と管理 ↑
3-1.共有の思想 ↑
| |
技術の蓄積 |
日常業務 |
| |
技術の体系化 |
自己研修 |
| |
知識の伝達 |
職員研修、プレゼンテーション |
| |
組織の改善 |
知識の共有の成果 |
3-2.作成の技術 ↑
3-3.ドキュメントの管理 ↑
検索演習 解答用紙 「◆例題3◆各県のインターネットの状況を調べる」について
県のページの評価
| 評価項目 |
評価 |
| 必須項目の記載:タイトル、更新日、管理者、連絡先など |
|
| 更新頻度:週一回程度 |
|
| 有用な内容はあるか |
|
| 出版の認識:ホームページは出版物 |
|
| 見やすさ画面構成:大きい画像は不可 |
|
| わかりやすい構造:全てを見渡せる |
|
| サーチエンジンへの登録:広報する |
|
Q1:県のネットワーク政策はどうなっているか?
Q2:県のネットワークの名称は?
Q3:県のページから、図書館へのリンクや図書館の案内へのリンクはあるか?
Q4:図書館に関する情報はどの程度まで公開されているか?
Q5:図書館のホームページはどうなっているか?
Q6:OPACはあるか? 収録点数は? 検索の手引きはわかりやすいか?
Q7:その県の有名な人物(歴史的、芸能人など)の詳細情報を、検索エンジンで探す。
Q8:次の8冊の図書を全て所蔵している図書館はどこか?