学術雑誌(外国雑誌)の効果対費用 主催:INFOSTA
日時:1999年4月15日(木)14:00-17:00
会場:国立教育会館6階602会議室
外国雑誌の価格問題と図書館の生き残り戦略:電子ジャーナルは代替とはなりえない!
長谷川豊祐(鶴見大学図書館)
e-mail:
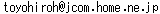
1.鶴見大学図書館の状況
a) 購読中止の概要
| 歯学部(一般雑誌) 予算:7,000万円 |
|
年度
|
中止点数
|
中止金額
|
備考
|
| 1995年 |
6点
|
450万円
|
CA, BA等 |
| 1996年 |
31点
|
750万円
|
一次資料 |
| 1997年 |
67点
|
720万円
|
一次資料 |
| 1998年 |
79点
|
1,380万円
|
一次資料 |
| 文学部・短大部(一般雑誌) 予算:1,000万円 |
| 1998年 |
50点
|
200万円
|
図書館学 |
| 逐次的図書 |
| 1997年 |
93点
|
280万円
|
歯学部 |
| 1998年 |
95点
|
230万円
|
文学部・短大部 |
b) 1998年度の購読中止の手順
6月:renewalの推計額−予算額=削減目標
8月:中止候補リストを作成
9月:図書委員会での調整・修正・承認
10月:契約
11月:支払
1月:いくつかのタイトルの復活・新規購読
注)重複購入タイトルなし、予算増額なし、DDS代替なし
2.各国通貨換算レート1982年比
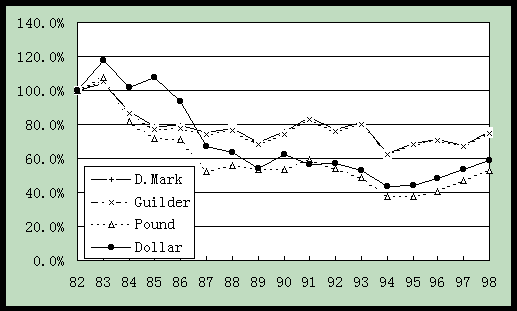
実勢レート(82-93:関ブロ、94:東大、95-:鶴見)
| 係数 |
1.219
|
1.195
|
1.175
|
1.176
|
1.19
|
1.245
|
1.225
|
1.182
|
| 年度 |
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
| 基準日 |
10/ |
10/ |
10/ |
10/ |
10/ |
10/ |
10/ |
10/ |
|
1-15
|
1-15
|
1-15
|
1-15
|
1-15
|
1-15
|
1-15
|
3-14
|
| D.Mark |
103.34
|
107.53
|
90.28
|
81.25
|
81.79
|
77.84
|
80.14
|
71.78
|
| Guilder |
93.25
|
98.44
|
80.57
|
72.11
|
72.54
|
68.88
|
71.26
|
63.7
|
| Pound |
430.7
|
463.31
|
352.84
|
309.02
|
307.64
|
225.42
|
241.91
|
229.43
|
| Dollar |
230.45
|
270.97
|
234.25
|
247.94
|
215.98
|
155.17
|
146.23
|
125.2
|
|
1.153
|
1.143
|
1.147
|
1.18
|
1.158
|
|
1.18
|
1.11
|
1.11
|
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
| 11/ |
11/ |
11/ |
10/ |
10/ |
10/ |
9/ |
10/ |
9/ |
|
1-15
|
1-15
|
1-15
|
1-15
|
1-15
|
1-15
|
1-30
|
1-7
|
1-15
|
|
78.22
|
87.23
|
79.88
|
84.07
|
65.27
|
71.28
|
73.69
|
70.11
|
78.65
|
|
69.31
|
77.34
|
70.88
|
74.65
|
58.27
|
63.63
|
65.72
|
62.26
|
69.68
|
|
230.71
|
256.77
|
233.98
|
211.09
|
161.88
|
163.27
|
175.25
|
201.73
|
229.14
|
|
144.37
|
129.97
|
131.02
|
121.38
|
100.71
|
101.69
|
110.77
|
122.82
|
135.53
|
3.外国雑誌の価格上昇への対応
vs出版社:購読中止
vs図書館:雑誌(情報流通)へのタダ乗りへの疑問
vs代理店:高額誌の直接購読、競争見積り
vs図書館:利益縮小への疑問
vs管理者:利用者,財務担当,経営者との共通認識
雑誌購入のための資金をかき集める
vs図書館:図書館経営効率の悪さ
vs利用者:ドキュメントデリバリーによる文献提供機能を強化
学術情報流通の基礎知識を組織的に蓄積
vs図書館:拡大路線への幻想
4.学術雑誌の価格変動の背景
出版社の定価の上昇:
電子化への投資
購読者数の減少
物価上昇
M&Aへの費用拡大
為替レートによる変動
購入価格のばらつき:
出版社が設定する地域差別価格
代理店の仕入原価の差
図書館の予算規模
5.図書館の対応策のレベル
集中管理:複数部局による重複購入の一本化
資料費の範囲内:購読中止、競争入札、資料費の再配分
運営費までの範囲:ドキュメントデリバリー
図書館全体:アウトソーシング、電子ジャーナル
大学全体:図書館への重点配分
図書館界全体:分担収集、共同購入
教育界全体:コンソーシアム
6.図書館のハイブリッド化による対応:Hybrid Library
雑種(Hybrid)には、しばしば雑種強勢とよばれる現象がおこり、
親よりも長生きで成長もはやく、丈夫だという傾向がみられる。
高度化:電子媒体と紙媒体をミックスした資料提供
効率化:雑誌業務と参考業務を統合し,図書館サービスを再編成
共生化:関連業界とのマルチソーシング(共同運営)による共生進化
グローバル化:経済と情報のグローバル化に対応したポジショニング
7.今年度の対策:あらゆる資源をかき集める
現在考えていること
外国雑誌の全点見積もり
外資系の利用(リーズナブルなシステムへ)
チェックイン方式による省力化
電子雑誌の試験的な導入
ILLへの文献調達のシフト
人員の再配分、能力強化
障害となりそうなこと
外資系へのアレルギー(国内代理店との協力の優先)
一社集中(効率化)への不安
ネットワーク環境の整備の遅れ
効率的に再編成した組織に図書館員がなじめない可能性
◆◆serialst-j 学術情報流通メーリングリスト◆◆
◆1◆ serialst-jの概要
●名 称: serialst-j (シリアルスト・ジェイ)
●正式名称: serialst-j 学術情報流通メーリングリスト
●管理人: 長谷川豊祐 <http://www2d.biglobe.ne.jp/~st886ngw/>
●目 的:
学術情報の流通に関するあらゆるテーマについての議論・情報提供・オフミーティングを行う.
図書館,書店員,研究者,出版社の交流の場を設定する.
●内 容:
雑誌業務から派生する問題についての質疑応答
:雑誌の到着状況, 雑誌の購読,購読価格,アウトソーシング,創刊雑誌の案内
セミナーや講演会の案内、参加の報告・感想
今後の学術情報流通システムへの対応
:ネットワーク,ドキュメントデリバリー,著作権,電子雑誌,新サービスの案内
●参加資格: 学術情報の流通に興味のある方なら誰でも.
●利用制限:
メールの大きさは20Kbyte以内に制限されています.(最大で、60-80字*200行くらい)
NDS社による無料MLのため、広告主からの広告がメールの先頭について配信されます.
MLへの投稿は,参加者以外でもできます。
●トラフィック: 月10通ほど(予定)
●アーカイブ: serialst-j 書庫:手動で月に一回まとめてテキストファイルで保存
<http://www.geocities.co.jp/Berkeley/4105/index.htm>
●関連URL:
SERIALST 雑誌関連の議論・ニュース ,アーカイブの検索 (米国)
<http://www.uvm.edu/~bmaclenn/serialst.html>
lis-serials 雑誌関連の議論・ニュース,アーカイブの検索 (英国)
<http://www.mailbase.ac.uk/lists/lis-serials/>
Newsletter on Serials Pricing Issues 雑誌の価格問題 (米国)
<http://www.lib.unc.edu/prices/>
図書館関係メーリングリスト <http://www.libra.titech.ac.jp/ML.html>
●運営開始: 試験運用 1998年8月28日から
INFOSTA第30回夏期特別セミナー『学術雑誌の費用対効果』(1998.8.27-28)参加者に案内
◆2◆serialst-jの使い方
●メーリングリストへの参加
serialst-j-request@mx4.dns-ml.co.jp 宛に
Subject:(表題/題名)には,何も記述しないで
本文として
join serialst-j メールアドレス 例) join serialst-j 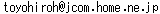
stop
を送る.
●メーリングリストへのメールの出し方
serialst-j@mx4.dns-ml.co.jp 宛に,普通にメールを出す.
メーリングリストへの登録者の全員にメールが送られます.
●最初の投稿は自己紹介を
登録がすんだら簡単な自己紹介メールを送ってみて下さい.
無料で提供されるMLなので,メールの先頭に5行ほどの広告が自動的にけられて届きます.
●メーリングリストからの退会
serialst-j-request@mx4.dns-ml.co.jp 宛に
Subject:(表題/題名)には,何も記述しないで
本文として
leave serialst-j メールアドレス 例) leave serialst-j 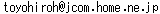
stop
を送る.
●●参考文献●●
●DDS
-
キャンベル, ロバート; ラッソン, デイビッド著: 窪田輝蔵訳. ジャーナルへのアクセス.
情報管理. Vol.39, no.4, p.258-299 (1996.7)
-
Hayes, John R. The Internet's first victim?. Forbes. Vol.156, no.14, p.200-201
(1995.12.18) インターネットの最初の勝利か? リード・エルゼビア:電子出版の伝統的出版事業への侵略』ルイジアナ州立大学図書館はエルゼビアの出版する
1,569タイトル、446,000ドルの雑誌をキャンセルして UnCover による文献提供に切り替えた。
-
特集=エレクトロニック・ドキュメント・デリバリー. 情報の科学と技術. Vol.44,
no.7, (1994.7)
●電子雑誌
-
時実象一. 学術計電子雑誌の現状. 情報管理. Vol.41, no.5, p.343-354 (1998.8)
-
カレン・ハンター. 私を眠らせない12の難問:学術雑誌をビジネスするには. 本とコンピュータ.
No.4, p.212-223 (1998春)
-
特集=電子ジャーナルとネットパブリッシング. 情報の科学と技術. Vol.46, no.7
(1996.7)
-
"The Electronic Journal: What, Whence, and When," Public-Access Computer
Systems Review. Vol. 2, no.1 (1991) p.5-24. 原文:Ann Shumelda Okerson
のホームページ<http://www.library.yale.edu/~okerson/alo.html> 翻訳:研究成果流通システムの研究開発
平成6年度報告: 平成6年度文部省科学研究費総合研究(A)(課題番号063020676)研究成果報告.
学術情報センター, 1995.3, p.1-15.
●書店・代理店の状況
-
洋書問題研究会. 岐路に立つ洋書業界. 出版レポート. No.34, p.46-53 (1997.6)
-
石岡克俊. 「手数料」に関する共同行為と競争の実質的制限:洋書輸入業者カルテル事件.
ジュリスト. No.1117, p.196-198 (1997.8.1-15)
-
西宮三雄. 洋書輸入販売業者による独占禁止法違反事件について. 公正取引. No.552,
p.56-61 (1996.10) 外国新刊図書購入について、六大協の価格交渉の方法は納入業者の独占禁止法違反行為を誘発するおそれもあり、個々に価格交渉をもつよう大学にも要請された。
-
山本康孝. 洋書輸入業者のカルテル事件. NBL. No.598, p.47-52 (1996.8.1) 外国新刊図書購入について
-
定期刊行誌などの契約状況が問題に:[会計]検査院が国立大学の雑誌購入などで.
会計検査情報. No.1877, p.8-9 (1990.8.16)
●コンソーシアム
-
特集=ライブラリーコンソーシアム. 情報の科学と技術. Vol.46, no.11 (1996.11)
●雑誌の価格問題
-
特集=外国雑誌の高騰にかかわる諸問題. 医学図書館. Vol.45, no.4 (1998.12)
-
特集=ジャーナルのコストパフォーマンス. 情報の科学と技術. Vol.47, no.2
(1997.2) 学術差しの価格形成(湊周二); 学術雑誌購読料金の高騰に伴う対応措置(久保田均);
外国雑誌の高騰:予算編成局の誤解と出版社に対する疑義(成田俊行); 外国雑誌高騰への対応(宮本智佳子);
オンラインジャーナルの利用と問題(中川真紀; 大原寿人)ほか
-
Will the chain breaker?: differential pricing as part of a new pricing
structure for research literature and its consequences for the future of
scholarly communication. Proceedings of an IFLA workshop, Stockholm, 23
Aug. 1990. Section on acquisition and exchange section on serial publications.
Edited by Ulrich Montag. K.G.Saur, 1992 (IFLA publication 61)
●学術情報流通
-
Mary M. Case著; 時実象一訳. ARLはSPARCプロジェクトを通して学術出版における競争を促進する.
情報の科学と技術. Vol.49, no.4, p.195-199 (1999.4) <http://home.highway.ne.jp/tokizane/Ref/ARL/ARLnf.htm>からも入手可能。 「Reed-Elsevierは1996年に、34億ポンド(57億ドル)の売り上げに対して、20.82億ポンド(35億ドル)の粗利益を上げている。税引き後利益6.04億ポンドのうち3.48億ポンドが株主への配当として支払われた後、2.56億ポンドが剰余となって残る」
-
New Journal Launched To Fight Rising Prices. Science. Vol.282, no.5290,
p.853-854 (1998.10.30) 従来から雑誌の値上がりに関する調査・提言を行っていたARLが音頭をとった
SPARCという団体が、商業出版者の雑誌に対抗する雑誌を学会と協力して来年、創刊する。Evolutionary
Ecology. (Kluwer)$777 に対抗して、Evolutionary Ecology Research. (Evolutionary
Ecology Ltd.)$305。Tetrahedron Letter. (Elsevier)$8602に対抗して、Organic
Letters. (American Chemical Society/APARC)$2300。Chemical Physics Letters.
(Elsevier)$8368に対抗して、PhysChemComm(Royal Society of Chemistry/SPARC)$353。出版者は、うまくいかないと、冷ややか。図書館は新規購入などできる余地はないということもある。 <http://www.arl.org/sparc/index.html>
-
宮川謹至; 小野徹. SICIを利用した自動チェックイン:LIRACS-II. 情報管理.
Vol.41, no.1, p.265-275 (1998.7)
宮
-
崎継夫. 国際コミュニケーションから見た日本の学術出版:人文・社会科学系を中心に.
出版研究. N0.28, p.147-157 (1997)
-
David Brown. The future of electronic information intermediaries : a survey
undertaken by DJB Associates on behalf of UKSG and JISC/ISSC. UKSG, 1996.9,
337p.
-
宮崎継夫. 日本の学術出版の国際化とその動向:自然科学系における現状と分析.
出版研究. N0.25, p.9-32 (1995.3) 海外への論文流出による国内欧文誌の深刻な経済状態と、外国の学会機関誌への「論文ただ乗り」という外国からの感情的な批判もある。
-
G.スティックス. 電子ネットワークと学術論文. 日経サイエンス. 1995年2月号
p.102-109. 原文:The speed of write. Scientific American. Dec. 1994.
-
Cummings, A.M. et al. University libraries and scholarly communication
: a study prepared for the Andrew W. Mellon Foundation. The Association
of Research Libraries, 1992.11, 205p. <http://www.lib.virginia.edu/mellon/
mellon.html>
-
Brookfield, Karen ed. Scholarly communication and serials prices. Bowker,
1991, 155p.
●学術雑誌の基礎知識
-
ACCESS NEWS編集局編. ACCESS NEWS Q&A 〜学術雑誌を取り巻く電子化の状況〜.
紀伊國屋書店, 1997.7, 70p. (ACCESS NEWS 創刊4周年記念号付録)
-
ACCESS NEWS編集局編. ACCESS NEWS Q&A 〜外国雑誌の基礎知識および実務〜.
紀伊國屋書店, 1996.7, 76p. (ACCESS NEWS 創刊3周年記念号付録)
-
バッシュ,N.バーナード. 図書館における定期刊行物の効果的な発注管理:アメリカの現場から.情報管理.
Vol.38, no.11, p.967-980 (1996.2) サービスチャージの額、欧米での代理店の売り上げの推計、その顧客館種の内訳(直接購読も含む)、館種・雑誌種別によるサービスチャージの幅、米国の大学図書館の状況、米国で購読される雑誌の原産国
-
窪田輝蔵. 電子ジャーナルと科学コミュニケーションのコスト. 医学図書館. Vol.43,
No.3. p.308-314 (1996) 「欧米では科学コミュニケーションのある部分に商業価値を認める。学会もまた市場を意識してジャーナルを運用しているし、営利出版社も積極的にジャーナルを発行している。Reed-Elsevier,
Springer, Blackwell, Academic Pressなど枚挙にいとまがない。彼らにとってジャーナルはビジネスであるから、コスト分析にきびしく、市場の動向には敏感である。このことはジャーナル出版のノウハウと財力の蓄積という点で日本と欧米の間の格差になって現れている。ジャーナルの電子化に投資できる経験と資金を欧米の出版社は培ってきた」
-
Schauder, Don著; 福島勲ほか訳. 専門論文の電子出版:大学研究者の態度と学術情報流通産業に対する意味(1)-(3).
情報管理. Vol.38, no.1, p.33-44 (1995.4); Vol.38, no.2, p.137-148 (1995.5);
Vol.38, no.3, p.233-245 (1995.6)
-
湊周二. 海外の学術情報の動向:欧米諸国における出版と流通を中心に. びぶろす.
Vol.46, no.3, p.47-52 (1995.3) 「日本では情報に関わる人々が小さいグループの中で物事の解決を図ろうとする傾向が強いのではないか。図書館人は、もっと出版社、取次、書店などと様々な問題を討議し、議論して現状認識を深めて行くべきであろう」
-
湊周二. 外国雑誌の現状と流通:取次店の立場から. 図書館雑誌. Vol.87, No.9,
p.663-664 (1993.9)
-
窪田輝蔵. 4-2 学術情報:先進諸国における出版と流通:米英を中心として. 図書館研究シリーズ.
No.30, p.419-459 (1993.3) 1.海外出版社の動向 1-A.英米出版協会の統計 1-B.学術出版の典型としてのSTM 2.出版社が見た市場:二つの市場調査 2-A.米国--AAP/ALA
Sutudy, 1987 2-B.英国--Book and Journal Spending; A Report, 1989 3.出版社の戦略:書籍、雑誌、Newsletter、Repackaging 4.取引の実体と条件 4-A.図書館市場 4-B.国際化、二重価格 5.わが国における外国出版物の需要予測 5-A.輸入洋書の量的実体 5-B.洋書輸入業者のシェア 5-C.学術研究と出版物需要の動向 6.洋書輸入業者のサービスの今後 6-A.販売総代理店の功罪 6-B.Order
Clearing Houseとしての業者 6-C.ポリシーミックス 7.その他、図書館を巡る諸問題 7-A.”日本型の情報社会”林周二の提起した問題 7-B.図書館第二出版市場論 7-C.図書館と出版社の冷戦(出版社は著作権、図書館は雑誌価格)
-
窪田輝蔵. 科学技術の生産・流通と図書館. 科学技術文献サービス. No.102, p.16-24
(1993) 1.はじめに 2.今欧米で何が問題になっているか?:学術市場における過剰生産と図書館の予算、営利か非営利か--米国の動き(ARLは非営利を指向しているが、営利なくして実際に可能なのか?)、出版第二市場としての複写市場 3.科学技術情報(STM
journal)はどのようにして作られているか?:編集と制作、費用の内訳と出版事業の利益構造 4.
科学技術情報(STM journal)はどのように売られているか?:価格政策、販売政策--書店の役割 5.今欧米の出版社は何を考えているか?:複写、電子情報ネットワークの開発、ペーパーレス
-
湊周二. 外国雑誌の差別価格をめぐって:輸入代理店の立場から. 図書館雑誌.
Vol.84, No.7, p.440-441 (1990.7)
-
Hazel Woodward and Stella Pilling ed. The international serials industry.
Gower, 1993, 275p.
●1970年代の動勢
-
<抄訳>学術雑誌に未来はあるか(1):学術雑誌に代わるべきもの. 情報管理.
Vol.17, No.2, p.117-126 (1974.5)
-
<抄訳>学術雑誌に未来はあるか(2):財政・技術的問題. 情報管理. Vol.17,
No.3, p.184-191 (1974.6)
-
<抄訳>学術雑誌に未来はあるか(3):学術雑誌の編集管理. 情報管理. Vol.17,
No,4, p.243-251 (1974.7)
-
<抄訳>学術雑誌に未来はあるか(4):学術雑誌の社会的かかわりあい. 情報管理.
Vol.17, No.5, p.315-322 (1974.8)
-
津田義臣. 学術出版物は沈没するか:米国の例にみる危機の様相(上)(下). 印刷界.
No.247, p.34-36 (1974.6); No.248, p.33-37 (1974.7)
-
小松三蔵. 外国雑誌の購入方法と問題点. 情報管理. Vol.18, no.12, p.951-958
(1976.3)
-
窪田輝蔵. 海外出版社の現状:学術雑誌を中心として. 私立大学図書館協会会報.
No.72, p.80-88 (1979.7)
●為替レート
-
宮森正和. ドル円レートの長期展望:2010年には50-70円の円高に. SRIC report
(三和総合研究所). Vol.4, No.1, p.1-6 (1998.12)
-
"平価切上げ" Microsoft Encarta 97 Encyclopedia. Microsoft Corporation. 「為替レートについて:第2次世界大戦後の日本円の歴史は、対外価値の上昇の歴史であったが、この間の固定相場制下での円の切上げは1度だけであった。終戦直後は商品ごとにことなったレートをもちいる複数為替相場制をとり輸出の振興をはかっていたが、1949年(昭和24)4月25日より1ドル=360円の単一レートが設定された。この固定レートの時代は20年以上つづき、そのもとで日本は戦後復興、高度成長をとげた。 1960年代後半になるとドルへの信任が弱まりはじめるとともに、日本の貿易収支の黒字基調が定着した。この時期には、1ドル=360円は当時の円の実勢と比較すると、円の過少評価(円安レート)になっていた。71年8月15日にはアメリカが金とドルの交換停止措置を発表し(ニクソン・ショック)、その後一時的に変動相場制度に移行したが、同年12月18日の10カ国蔵相会議で主要各国の新しい平価が決定し(スミソニアン合意)、日本円は1ドル=308円に切上げられて再出発した。これが日本円の戦後唯一の切上げ例であり、この時の切上げ率16.88%は各国間で最大のものだった。 しかしこのスミソニアン体制も長続きせず、1973年2月14日に日本は変動為替相場制度へと移行した。この変動相場制度初日のレートは1ドル=271円だったが、以後円はすう勢として増価をつづけ、95年4月19日には東京外国為替市場で一時1ドル=79円75銭という市場最高値をつけている。」
●文献レビュー
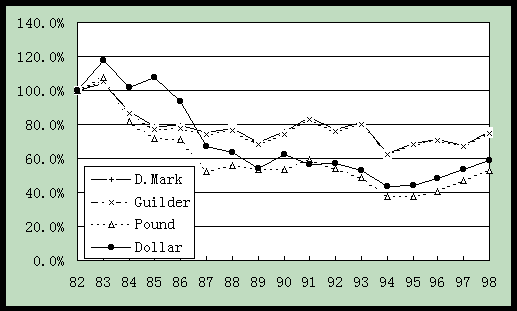
![]()
![]()